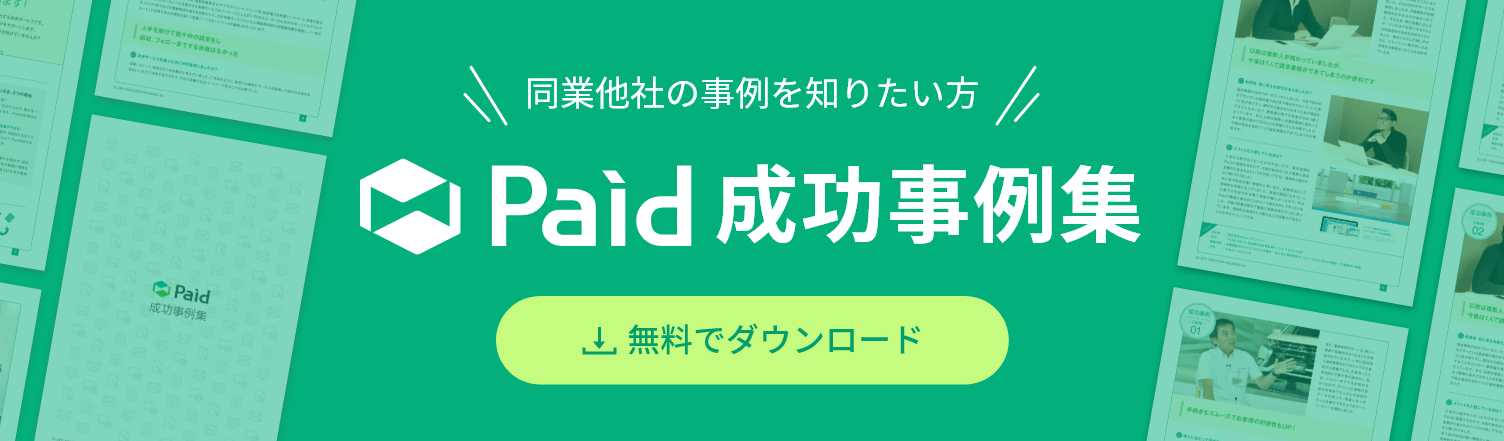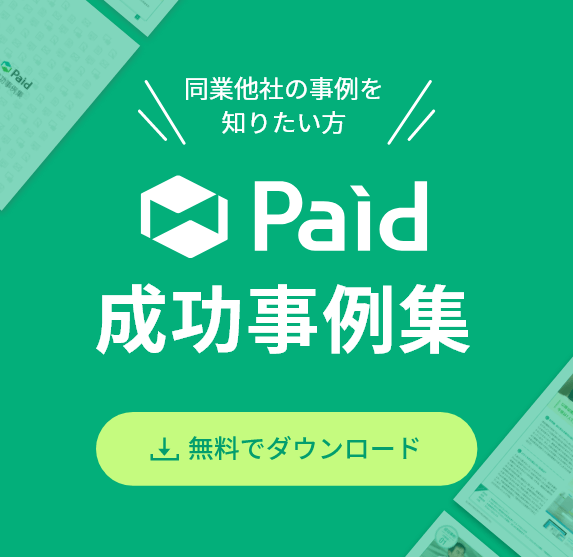支払督促・催促メールの書き方・例文~テンプレートや送信のタイミング
提供した製品やサービスの対価が支払われないと、企業は大きな損失を被ります。ダメージを最小化すべく、未払い発生時の対応では催促や督促のメールを送ることは不可欠です。
本記事では、督促 ・催促メールの書き方や送信時のポイントについて、例文を交えながら解説します。
- 目次
督促・催促メールとは
企業は提供した製品やサービスの対価を徴収するために請求書を送付します。もしも、この請求に対して何らかの事情で支払いが遅れたり、不履行となったりした場合、自社の資金繰りに影響が出てしまいます。そこで、支払いを促すために送るのが催促や督促メールです。
支払いの遅れを催促するメールは、相手を急がせる行為でもあるので、場合によっては失礼にあたる可能性もあります。そのため、メールの文面には細心の注意を払いましょう。
催促と督促の違い
催促と督促は、いずれも支払いを促す行為です。明確な意味の違いがあるわけではなく、支払いに対する強制力を伝えるニュアンスが異なるといえます。催促は、支払い期限が過ぎた際に、まずは支払い状況を伺いつつ支払いがない旨を伝えるために行われます。催促したにもかかわらず支払いがない場合に、督促によってより強く支払いを要求します。
督促では法的措置の可能性も伝えるため、より厳しい言葉遣いになることが多いです。
督促・催促メールの強制力
ビジネスにおいて、メールはスタンダードなコミュニケーションツールですが、メールでの督促には強制力はありません。あくまでも「お忘れではないですか」といったソフトな催促の位置づけであり、法的な効力はないのです。
とはいえ、取引相手に支払いが遅れていることを指摘するだけでも十分に意味はあるものです。
督促・催促メールの書き方
督促・催促メール に記載する内容は、主に以下の5つです。
1、件名
2、宛先
3、挨拶
4、本文
5、結び
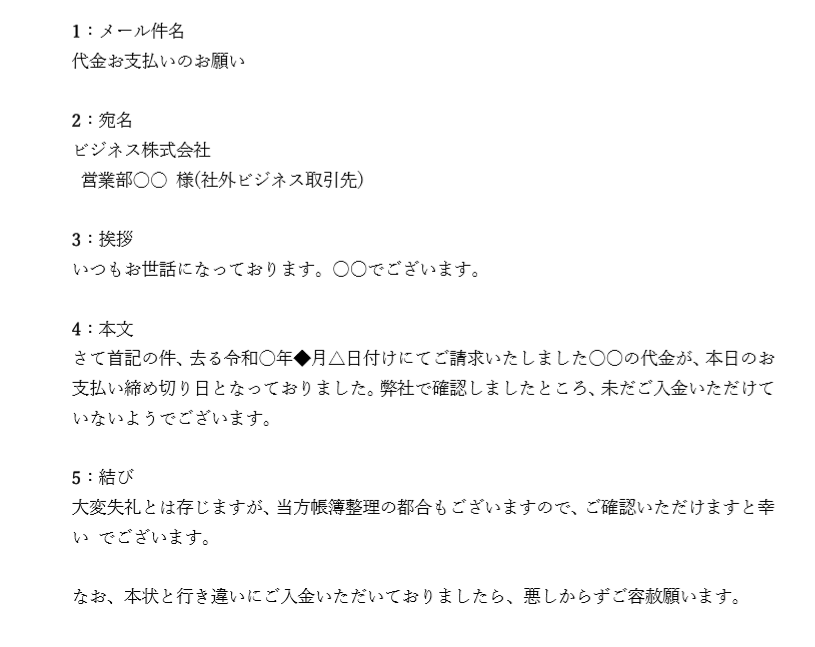
督促・催促メール はあくまでも気づきを与える程度のお知らせです。相手に非があるとしても丁寧な文面を心がけましょう。
件名
件名は、目的が督促や催促であっても高圧的な表現は避け、「代金お支払いのお伺い」や「支払い期限のご確認」など、あくまでも念押しのためであるという文言にすることがポイントです。
あからさまに催促や督促を押し出す件名は、それがたとえ事実であっても相手にとって不快なものです。常識的なビジネスマナーを順守してください。
宛先
一般的には、通常やり取りしている担当者宛に送ります。その際、会社名、部署、氏名を明記しましょう。また、担当者の上司のメールアドレスをCCに入れ、部署、氏名も記載して送ると少し踏み込んだイメージを与えることができます。
督促といってもあくまでメールの段階では「お知らせ」レベルです。できる限りソフトに、事を荒げないことを意識した対応を心がけましょう。
挨拶
続いて、挨拶のフレーズについて確認しておきましょう。
- お世話になっております。株式会社○○の△△でございます。
- 何度も失礼いたします。株式会社○○の△△でございます。
懇意にしている取引先であれば、「いつもお世話になっております」というフレーズが自然でしょう。
本文

本文には、以下の内容を記載しましょう。
- 請求書の送付日
- 請求書の内容
- 支払期日
- 入金状況
督促・催促メール の目的は、支払いが完了していないことを認知してもらい、確認を促すことです。そのため、どの案件に対する請求なのか。その内容と送付日を明記します。そして、支払いの締め切り日を記すことで、現状を把握してもらいます。
入金状況を伝える際には、あえて「支払われていない」と表現せず、あくまでも「入金の事実がない」という表現に止めることで、やんわりと相手の行動を促すことが期待できます。
結び
結びでは実際に相手にしてもらいたいことを記載します。ただし、「入金してください」とストレートに記載するのではなく、すでに入金済みである可能性も含め、あくまでも念のために送っているというスタンスから、「ご確認願います」という表現に留めておくのが無難です。
そのうえで、「本メールと行き違いでご送金頂いていただいておりましたら、なにとぞご容赦ください」といったフレーズを必ず添えましょう。
無料
公開中-
アフターコロナ時代に
必要な与信管理とは?資料をダウンロードする
督促・催促メールの例文・テンプレート
2回目以降の督促・催促メール
2回目以降のメールは、件名の冒頭に「【再送】」を入れることで、目に留まりやすくなる可能性があります。
挨拶に関しては、何度目かの催促メールの場合は、「何度も失礼いたします」という文言が適切です。また、複数回メール送信する場合は、「行き違いで連絡をいただいておりましたら申し訳ございません」といった文言を入れるのも誠意が伝わり、不快な印象を薄めることにつながります。前回の督促メールについても言及すると親切です。
催促・督促メールを複数回送っても支払いがない場合は、結びの言葉に法的措置を検討しているなど、より強く支払いを求める姿勢を明示しておきます。
以下に、挨拶・本文・結びの例文を以下に記します。
挨拶
度々のご連絡失礼いたします。
本文
先日のメールにて、◯月◯日付の請求書についてご入金のお願いをいたしましたが、□月□日時点でまだ入金の確認ができておりません。 お忙しいところ大変恐縮ですが、ご状況をお伺いできますと幸いです。
結び
◇月◇日までにお支払いがいただけない場合は、誠に遺憾ではございますが、法的手続きに移行させていただく可能性がございます。
万が一、既にご入金いただいている場合は、行き違いのご連絡となりますことをお詫び申し上げます。
督促・催促メールを出すタイミング
メールでの催促・督促は、支払期日の当日でも問題ありません。その際は「本日ご入金いただけそうでしょうか」とした文面であれば自然です。
期日を過ぎてしまったタイミングでは、「〇日までにお願いしておりましたが、状況はいかがでしょうか」と促しましょう。催促メールを送る目安は、支払期日から3日~1週間程度経ってからが一般的です。
このタイミングの催促で入金されるケースは、単純なミスが原因である場合が多いので、顧客との良好な関係を保つために、確認をお願いする姿勢でメール文を考える必要があります。
2回目の催促メールを送る場合は、1回目の送信から3日程度空けて送るといいでしょう。複数回連絡しても支払いがない場合は、メールだけにとどまらず、電話や書面での連絡も併用し、法的措置を含めた警告をします。
督促・催促メールを出しても支払われない場合
催促・督促メールに返答せず支払いに応じてくれない場合は、以下の措置をとることになります。
催促メールを送っても反応がない場合、督促メールか催促状で支払いを促します。
効力の強さ: 催促メール< 催促状< 督促メール< 督促状
これらはメールで可能な限り支払いを促してから書面を郵送するのか、最初のメール以降は書面で支払いを促すのかの違いです。
なお、督促メールと催促メールの内容自体に大きな違いはありません。
内容: 催促メール= 催促状= 督促メール= 督促状
1、催促状を手紙で送付する(あるいは、督促メールを送信する)
2、督促状を手紙で送付する
3、内容証明郵便で文書を送付する
4、裁判で解決する
催促メールに相手が応じてくれない場合は、文書による催促状を郵送します(あるいは、督促メールを送信します)。それでも返事がなければ、督促状を送付し、督促状を送っても返事がないようであれば、今度は内容証明郵便で文章を送付します。これによって、「受け取っていない」という言い訳は通用しなくなります。なお、督促状を送付する2の時点で法的措置を前提とするしないにかかわらず、「受け取っていない」「見ていない」というトラブルを避けるため、内容証明郵便で送付するのがおすすめです。
これも無視すると、状況次第では裁判手続きに進むことになります。裁判所から督促状が送られ、相手の出方次第では裁判となります。
督促業務の効率化と未回収を防ぐ方法

企業間決済代行の「Paid(ペイド)」は、督促業務を含めた請求業務をすべて代行し、万が一未回収になった場合も代金を100%保証します。Paidを利用することによって、督促の手間を解消し、また未回収の心配をする必要がなくなります。
Paid導入で督促の手間や未回収リスクを解消した事例
Paidの導入により督促の手間や未回収リスクを解消できた事例を紹介します。
| 導入企業 | 株式会社生活の木 |
|---|---|
| 業種 | アパレル・雑貨 |
Paid導入前の課題
営業アシスタントが月に2回督促業務を行っていましたが、毎回督促状を出力して封入して発送してという業務に2~3日はかかっており、本来やるべきアシスタント業務に集中できないというのが課題でした。
また請求書を送って終わりにしてしまう件数も多く、そうなると未回収もその分増えてしまい、督促の件数が全く減らないという状況が続いていました。
Paid導入後の効果
これまで督促業務のようなマイナスをゼロにする仕事に営業アシスタントの時間がとられてしまっていたのが、今はページを作ったりメルマガを作ったりという、プラスを生み出す仕事に転換できています。未回収のリスクもないため、攻めの体制につながっています。
プラスを生み出す仕事に集中できるように!大きな限度額で売上もUP~株式会社生活の木の事例
まとめ
ビジネスでのもっとも大きなリスクのひとつが未払いです。代金が回収できなければ資金繰りへの影響はもちろん、それを回収するために本業の時間が削られ、生産性が低下してしまいます。
請求業務を代行するサービスの活用は、その回避策としてもっとも有効な手段のひとつです。請求・未払いへの対応といった課題を抱えているなら、請求業務代行サービスの導入をご検討ください。